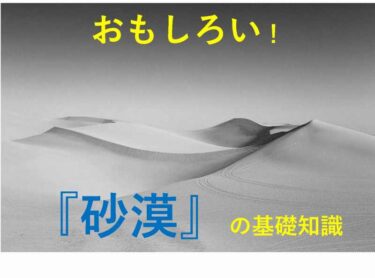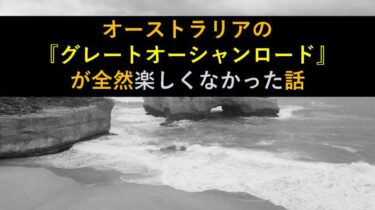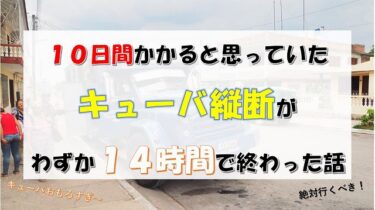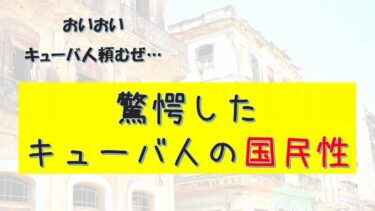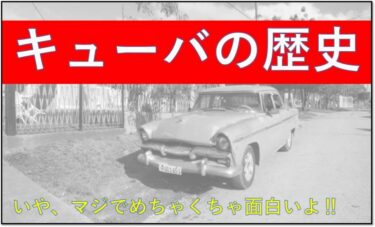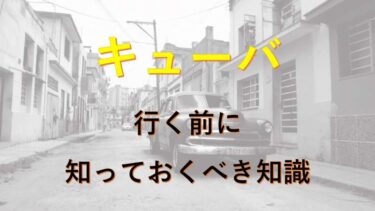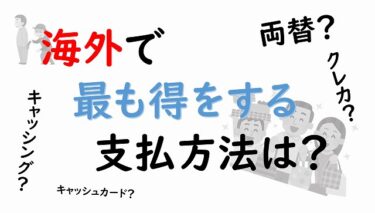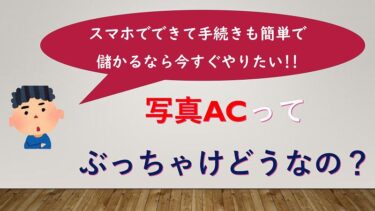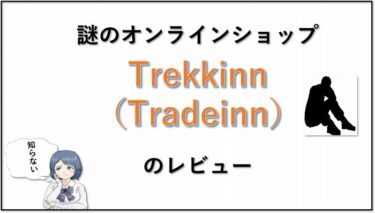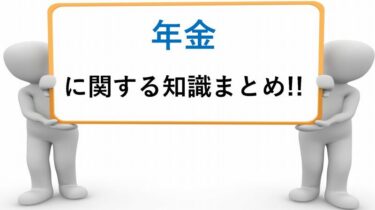先日「風力発電と太陽光発電が砂漠の緑化に貢献する」という研究報告を目にしたときに、自分も以前実際にオーストラリアの砂漠でテント泊したことを思い出した。
まさにこれが、筆者がこの記事を書こうと思ったきっかけである。
筆者は2017年11月に2週間オーストラリアへ行ってきた。
この大冒険の最初の1週間、筆者はメルボルンに住む知り合いの家で「ありがたや、ありがたや」とひたすら甘えて過ごし、残りの1週間は「おれは自由だ!」と叫びながらレンタカーを借り、どこへ行くのか、何をするのか、全く計画なしで好き勝手に行動した。
まさに「好きなことして、好きなだけ遊んで、気が向けば帰る」というスタイルで楽しみ尽くしたのである。
さて、そろそろ本題に入ろう。

皆さん、砂漠ってどんなイメージだろうか。
- 星がキラッキラに輝いてる
- 空気がピュアで、逆マスクしないと死ぬほどキレイ
- サソリとかクモとか、恐ろしい生物がごろごろしてる
- 昼はオーブンくらい暑く、夜は冷凍庫くらい冷え込む
- たまに、謎のオアシスが現れる
たぶん、誰に聞いてもこんな感じじゃないだろうか。
そして、砂漠でテント泊するという夢を抱いていた筆者が体験したのは、感動と危険がパーティーしているような世界だったのである。
もし「砂漠の基礎知識」に興味のある方は先にこちらをご覧ください↓(別タブで開きます)
筆者は過去にオーストラリアの沙漠で野宿した経験があるのだが、当時は沙漠について完全無知。サボテンが勝手に水を出してくれるとか、蜃気楼が飲み水に変わるとか、ディズニー的発想で乗り切ろうとしていた自分を往復ビンタで正したい。[…]
オーストラリア旅概要~前編~
筆者はメルボルンでお世話になったD氏に別れを告げ、一人でレンタカーを借りて、オーストラリアの南海岸沿いをアデレードまで旅することにした。
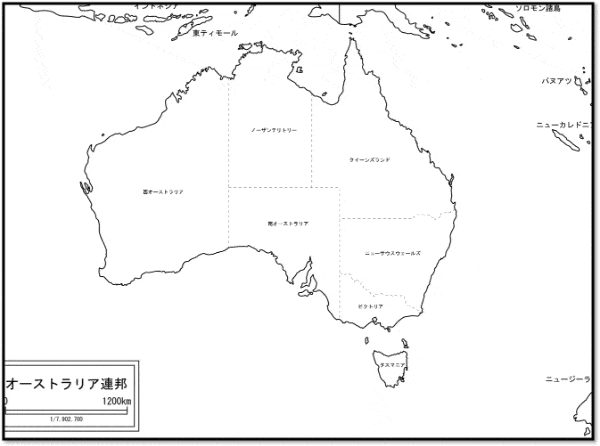
直線距離だとちょっと短いが、海岸沿いに走ると約1,000kmという距離らしい。
ちなみに、この距離は札幌から富士山までくらいだと言われている。
筆者「札幌から富士山って…やばくね?」
ちなみにオーストラリアの面積は日本の20倍もある。
- 一体自分がいまどこにいるのか?
- 大きな町(目的地)まであとどれくらい走るのか?
- 次のガソリンスタンドまで燃料がもつのか?
など、多くの不安を抱えながら、過ごしていた。
たまに立ち寄った町で紙の地図を手に入れて、「あ、ここまで来たのか。なんとか生き残れるかな」と自分の位置を確認することでなんとか心の平穏を保っていたのである。
メルボルン(出発地)
メルボルンは世界一住みやすい都市6年連続1位を誇るオーストラリア第2の都市である。


メルボルンで一週間過ごした感想は
「都会なのに緑が多く、広々している!!!!めっちゃいい。」
世界一住みやすい都市と言われる理由もわかる気がした。

都会は都会でも、よくある人混みでギュウギュウ、狭くてゴミゴミ、通りはタバコの吸い殻と鳩のフンで埋め尽くされ…みたいな、あの雑多な感じの都会ではない。
いや、まったく違う。
そもそも国の面積が日本の20倍もあるオーストラリアである。
歩道も広けりゃ車道も広い、建物の間にも余白がありまくりで、見渡す限り「落ち着いて生きていいよ」と言わんばかりの空間設計。
結果、非常に穏やかでのびのびとした暮らしができそうな都市であった。
心なしかカモメものんびりしていた。

筆者はこのメルボルンで1週間ゆったり過ごし、そしてついにアデレードに向けてレンタカーで旅立ったのである。
車に乗り込む筆者の背中には、どこか風のような自由と、ちょっとした不安が同居していた。
まあ、主に不安の方が大きかったのだが。
さて、そのレンタカー屋で目にしたのが、「カンガルーやコアラに当たったときのための保険」
……いや、ちょっと待て。そんな保険がある時点で、「当たる可能性、けっこうあるやん」と思わざるを得ないわけである。
だが、筆者はこの保険に入らなかった。なぜか。
だいぶ年上のD氏が言ったのである。
「俺は人生で一度もカンガルーもコアラもはねたことがない」と。
……それを聞いた筆者は、「ならば大丈夫だろう!」という極めて根拠の薄い自信に満ちた判断を下し、保険には入らず出発した。
命運をD氏の人生統計に託すという、謎のロジックである。

カンガルー衝突注意の看板(笑)
しかしながら、猛スピードで運転中にカンガルーやコアラと衝突すれば、当然ながら彼らは命を落とすであろうし、こちらのレンタカーも無傷では済まない。
Youtubeでクマやシカとの衝突動画を見る限り、どうやら車もかなりの壊滅的ダメージを受けるらしい。
つまり、ぶつかった瞬間、「あっ、詰んだな」と思う程度にはヤバいわけである。
いやほんと、冗談抜きで「あ…これ、リアルであるやつやん…」と静かに思った。
ちなみに、D先生のご自宅のすぐ裏の公園には、なんと野生のカンガルーが普通に遊びに来ていた。しかも筆者も実際に目撃済み。
…だがしかし、その実物がとにかくごつい。
言葉にできないほどマッチョなのだ。
遠くから見てるだけで、「あれ…今、こっち睨んだ?睨んでたよね?」と無駄に心拍数が上がるレベル。
よって、カンガルーはただのモフモフジャンパーではない。
危険生物枠に堂々エントリーさせておくのが賢明である。
近寄るときは敬語と目下の態度を忘れてはならない。
アデレード(目的地)

目的地であるアデレードは、正直なところ「これが名物です!」というド直球な名所はあまり無い。だがしかし、筆者が訪れた時期は「クリスマス前」であった。
つまり、街はすでにテンションMAXの大騒ぎモードに突入していたわけである↓

そう、南半球の夏のクリスマス。初体験である。
「Last Christmas」がしんみり流れて、イルミネーションが雪に反射して…みたいな、日本のしっとり冬クリスマスとは完全に別物。
こっちはもう、完全にカーニバルである。
サンタも汗だく、トナカイもたぶん冷房を探してる。
筆者がアデレードにいたのは、ちょうどクリスマスの1か月前くらいだったのだが、すでに街では大規模なパレードが道を占領して大行進していた。
信号?知るか!って勢いで歩く人々。
音楽は爆音、観客は大盛り上がり。
この勢いなら、たぶん11月頭からサンタが準備運動してるに違いない。
また、パレードが通過したあとの大通りはというと。

地面一面がチョークの落書きで埋め尽くされていた。
もうこれは「子どもたちの作品展 in アスファルト」と言っても差し支えないレベルである。
お絵かきの内容は、サンタだったり、謎の動物だったり、もはや何かの霊的な存在っぽいものまで幅広く、見る側も想像力を試されるアート空間。
子どもたちにとっては最高のキャンバス、そして親にとっては服が汚れる覚悟の遊び場である。
まさに「すべてを無に帰すマシン」。
あの清掃車、正直ちょっとカッコよかった。
オーストラリアの砂漠でテント泊~前編~
さて、先に始点(メルボルン)と終点(アデレード)について語ったが、ここからが本題である。
オーストラリアのメルボルンから海沿いルートでアデレードを目指すと、途中で必ず通るのが「グレートオーシャンロード(通称GOR)」である↓

筆者がこの片道1,000kmの旅で運転したうち、約280kmがこのGOR区間。
つまり全体の約1/4以上を「グレート」と名のつく道路に費やしたことになる。
ただし、先に白状しておくと筆者的にはこのGOR、ぶっちゃけあまり感動しなかった。
感動値でいえば、コンビニのレシートに偶然「777」が揃ったくらいのレベル。
そのあたりの詳しい話は以下の記事で語っているので、恋人や友人とこれから行こうとしている人は一度目を通しておくと後悔が減るかもしれない。
RYOです皆さんも一度は耳にしたことがあると思います、グレートオーシャンロード(Great Ocean Road)!!※現地ではGORと略されますので以降GORと表記します。筆者は2017年11月にメルボルンからレン[…]
グレートオーシャンロードは名前の通り、基本的には海岸沿いの道路である。
だが、ずっと海沿いを快走できるかといえば、そう甘くはない。アデレードに近づくにつれて、GORは徐々に内陸へと吸い込まれていく。
その結果、何が起こるか。
——海が消える。
——そして現れるのは、砂漠。

適当に停まったり休憩したりしながら、こんな道を毎日何時間も走り続けるのである
以降、筆者は海風を感じる旅人から、照りつける太陽の下、乾いた道路をひた走るサバイバーへと姿を変えるのであった。
GPS?Wi-Fi?そんなものは文明の象徴であり、ここには存在しない。地図と看板だけが、筆者を導いてくれる唯一の道しるべであった。
「暗くなってきたな……よし、パトロールに見つからんように、砂漠にそっと入り込んでテント張るか」
という、もはや時間も法律も概念もバグったような生活をしていた。
普通の旅行者が聞いたら絶句するタイプの行動パターンである。
1,000kmも走っていると、時にはかすかにピンク色を帯びた海がちらりと見える。

すると筆者は車を停めて、まるで幻を追うかのように海辺まで歩き、写真を撮る。

おそらく犯人はプランクトンだろう、このピンク色の正体は。
ま、知らんけど。
このあたりの行動力は、もはや旅人というより狩人。
途中、テントや服が湿ってきたら、「これは放置したらカビるやつやな」と察し、誰もいない道路脇で堂々と天日干し↓

景観とかもう知らん。
テントの寿命の方が大事である。
また、ぽつりと現れる小さな町に出くわすと、
「なにか掘り出し物があるのでは……」という希望を胸に、マーケットを覗いてみたりもした↓

野生動物並みの勘で行動しているが、心は意外と庶民。

つまりこの頃の筆者の生活は、
「明るくなったら動き出し、暗くなり始めたらテントを張って寝る準備をする」
という、完全に原始人スタイル。
時計もスマホも用済み、
本能と太陽だけが筆者の生活リズムを決めていたのである。
当時の筆者は(つまり完全に旅人モードで本能のみを信じていた筆者は)「車中泊・テント泊が禁止されている」などという常識は一切知らなかったわけである。
いや、知ってたらやってなかったかというと、まぁ、それはまた別の話だが…。
どうやらオーストラリアでは、基本的に正規のキャンピングスペースをお金を払って借りて泊まるのがルールらしい。
つまり、筆者が夜な夜な砂漠に忍び込んでテントを張っていたあの行為、あれは完全に「アウト」であった。
テント泊禁止について、今さらながら思うのだが——
たぶんあれ、ただのマナーとか治安とかの問題ではなくて、
「いやマジで危ないからやめとけ」って意味だったんじゃないかと思う。
なんせここはオーストラリア。
地球上でトップクラスに「おまえ、何でそんな毒持ってんの?」という生き物がうようよしている国である。
毒グモ、毒ヘビ、毒を持ってそうな見た目のカエル、その他よくわからんけど見たら逃げたくなる系の生物たち。
そんな彼らの縄張りに勝手にテント張ったら……それはもう、夜中に「こんにちは」されても文句は言えない。
テント泊解禁などしようものなら、翌朝のニュースで「またひとり旅人が犠牲に…」という見出しが並ぶことは間違いなしである。
食事の調達
オーストラリアという国は、もうほんと、とにかく広い。
日本の約20倍、広すぎて感覚がバグる。
そのため、海岸沿いを走っていても町は点在しており、「次の町まで3時間ノンストップで走る」なんてのはもはや日常。
軽いドライブ感覚で出発したら、「あれ、もう東京から名古屋まで来てるやん…」みたいなことになる。
広すぎるのも問題である。
診療所、銀行、郵便局、そして謎のトーテムポール的なモニュメントまで、わりと何でもある。

そして、筆者が特にお世話になったのが「Coles(コールズ)」という大型スーパーである。
食料品はもちろん、DIY工具、衣料品、医薬品、たぶん頼めばカンガルーのエサまで出てくるんじゃないかってくらいの品揃え。
筆者が選んだこの日のディナー、それはずばりステーキ!
値段は正確に覚えていないが、とにかく安かった。
もちろんステーキソース、胡椒、塩などの調味料もフル装備で購入し、あとは次の町までひたすらドライブ。
何時間かかるのか?そんなこと知らん!とりあえず走れ!
そんな感じで再び荒野を突き進んだ。
腹が減ってもテンションは高い、野生の旅は胃袋から。
テント泊
そしてその日も、筆者は例によって「これ地球か?」と疑いたくなるほど無限に続く砂漠ロードをブーーーーンと突き進んでいた。
車窓の景色はひたすら「砂→草→草に見えるけどトゲの塊→謎の鳥→また砂」
もはやパターン芸である。
そんな中、真上でギラついていた太陽が「そろそろ帰るわ」と言わんばかりに西へ傾き始める。
これがまた早い。
さっきまで「おいおい熱中症で倒れるかも」と思ってたのに、気づけば「やばい、これ熊出るやつやん…」ってくらい暗くなってくる。

「さーて、今晩はどこで寝ようかな~」
というわけで筆者、砂漠に面した広場っぽいエリアに車を停める。
が、ここでの寝床選びにはコツがある。
ズバリ「人に見られず、かつ毒蛇にも出くわさない場所」
そんな都合のいいスポットがどこにあるのかは知らんが、とりあえず木陰へGO。
なんとなく「この木ならバレんやろ」と思い、愛用のテントをモソモソ設営。
この時点で完全に「野営」というより「潜伏」。
どこのスパイ映画やねん。
さてさて、ここから筆者のどうでもいい思い出話を始めようか……と思ったが、待ってくれ。
その前にひとつ、この広大すぎるオーストラリア砂漠の、
「感動と恐怖のダブルパンチ」
を、まずはお見舞いしようじゃないか。
(別タブで開く)
先日「風力発電と太陽光発電が砂漠の緑化に貢献する」という研究報告を目にしたときに、自分も以前実際にオーストラリアの砂漠でテント泊したことを思い出してこの記事を書こうと思い立ったわけです、はい。筆者筆者は2017年[…]
先にこちらを読まれてからの方が楽しんで頂けると思っている。
オーストラリアの砂漠でテント泊~後編~
ではここから、筆者のどうでもいいけど聞いてほしい思い出話・後半戦に突入する。
まずは、大きな木の陰にひっそりテントを張った筆者。
キャンプの第一歩はもちろん…写真撮影である。
SNSに載せる気もない、誰に見せるわけでもない。
だが撮る。記録こそが男のロマン。



陽が沈む瞬間って、なんであんなに見飽きないのだろうか。
……いや、マジで30分ずっと見ていた。
夕陽が水平線にスーッと沈んでいき、やがて辺りは闇。
ほんとに「漆黒」というやつ。
街灯?ない。月明かり?出勤拒否。
頼れるのは己のヘッドライトと、若干ぬるくなったペットボトルの水だけ。
そしてお待ちかね、ディナータイム!(^ω^)イェイ
本日のメニューはというと…
\ドンッ!!/
砂漠のど真ん中で豪快にステーキ!!
肉だ!火だ!夜だ!
これはもう原始人ごっこと言っても過言ではない。

筆者は、Colesで買い揃えた肉・塩・胡椒・ソースのフルコンボを持参しており、「俺の料理に足りないのは厨房だけだ」状態でクッキングを開始。
火加減なんて知らん。
肉が焼けてるっぽい←食べる。それが旅人の作法である。
いやあ、あの瞬間だけはたぶん、どんな高級レストランで食うシャトーブリアンよりもうまかった(知らんけど)。
なにしろ、隣が砂漠、上は満天の星空、そして誰もいない。

…って、冷静に考えたらちょっと怖いが、そこは目をつむっておこう。
その後、テントに入って寝るだけ。
文明から完全に切り離されると、人間は意外とすぐ原始に戻れるものだ。

久しぶりに食べた肉は格別に美味しく、その後、鍋やフライパンを洗うための水がないので、そのままテントの外に置きっぱなしにして臭いを散らす作戦を決行。
「テントの中に置くと嫌な臭いがつく」かと言って「外に置きっ放しだと虫がたかりそうで嫌だ」、ということで仕方なくテントの前室(テント本体と外との間のスペース)に置いておいた。
この決断が後々、トンデモナイことに繋がるとは、この時の筆者は知る由もなかった。
その後、筆者はステーキを残さず食べ、砂漠の絶景を心ゆくまで満喫し、満足感に浸りながら眠りについた。
しかし、夜中のこと。時間はわからないが、おそらく2時か3時くらい。
突然、テントの外から、いかにも肉食獣らしい唸り声と足音が聞こえてきたのである。
「ハッハッ、ヴゥゥ~~、ハゥ~、ヴァウ~」
筆者は一瞬、「まさか、オーストラリアにこんなにもリアルなシーンが待っていたとは…」と思いながらも、最初はのんきに構えていた。
「まあ、野生動物だろう。カンガルーか何かが通りかかったんだろう」と、若干楽観的だったかもしれない。
しかし、その音はどんどん近づいてきて、次第に筆者の楽観的な思考をも崩し始めたのであった。

筆者は日本国内でもテント泊の経験が豊富である。
山の中でテントを張っていると、サルやクマ、シカ、ウサギなど、動物たちがテントの周りをうろつくなんてことは日常茶飯事だった。
だからこそ、この時もパニックにならず、冷静に構えていられたのかもしれない。
「いや、動物なんてそんなもんだ。ウサギがちょっと近くに来たのか、サルがテントの中を覗いてるだけだろう」と、自己暗示をかけながらも、耳を澄ませてその音を聞く。
だが、なんだか今までとは少し違う。
少なくとも、日本の山で感じた安心感とはまるで別物だ。
気づけば、筆者の背筋が少しだけ冷たくなってきていた。
オーストラリアの砂漠地帯・・・?犬っぽい雰囲気?
犬っぽい、犬っぽい…ん?
オーストラリア、砂漠、イヌ科?
え、まさかディンゴ?
筆者はディンゴについての知識が全くなかったが、その時、テントを破って襲ってきそうな気配を感じ、心底恐怖を覚えた。
それから体感では2時間ほど、息を殺して目を閉じ、右手にはVICTORINOXのRANGERという手のひらサイズの21徳ナイフを握りしめながら、冷や汗をかきまくり、足音が消えるのをひたすら待っていた。

筆者が持っていたVICTORINOXのナイフ
「これで羊を食べる肉食獣と戦えるのか?」
この時の恐怖と言ったら、もう言葉では言い表せなかった。
頭の中で、もしもの時にどうやって戦うかのシュミレーションを繰り返しながらも、心の中では、ひたすら「どうか、どうか近づいてこないでくれ。いや、来ないでください。」と祈り続けていた。
おそらく、ステーキの匂いに誘われてやってきたのだろう。
緊張で心臓がバクバクして、冷や汗がじわじわ出てきた。
まるでサウナで過ごしてるかのようだったが、足音は次第に遠ざかり、とうとう完全に消え去った。
その瞬間、筆者の頭の中はお花畑に変わり「あれ?もしかして、ただのカンガルーかな?」と思い始めた。
ヤツらは室伏広治並みのフィジカルモンスターである。
「いや、もしかして、宇宙人かもしれないぞ!」
「ワハハ、でもまあ宇宙人なら友達になれるかも」
「いや、でもそんなことよりステーキが美味しかったからもういいや♡」
などと、思考が完全にパラレルワールドへ突入。
そして、すべてを放置して(いや、むしろ放置したくなって)筆者はそのままぐっすり寝ることができたのである。
心地よい砂漠の風が肌を撫で、満天の星空が広がるその下で、まるで時が止まったかのように静寂が支配する中眠りにつくことこそ、最高の贅沢である。
おしまい。
さいごに

今回はオーストラリアの砂漠でのテント泊について話したが、筆者はもっと多くの砂漠を旅してみたい。
砂漠でテント泊をしたり、ラクダに揺られながら広大な大地を進んだり、ドローンを飛ばして砂の中に隠された秘密を暴いたりしたいものだ。
砂漠というのは、生物が生存できるギリギリの限界地点。
その過酷な環境の中で生き延びている生物たちは、独自の進化を遂げているのだろう。
そんな場所で実際に暮らせば、周囲の人々や環境のありがたみが、ひとしお深く感じられるに違いない。
だから、あまり怖がらずに、テントを持って、広大な砂漠に挑んでみるのもいいかもしれない。
きっと、想像以上の発見と感動が待っているはずだ。
ちなみに、オーストラリアの話から少し逸れるが、キューバの記事も好評なので、ぜひチェックしてみてほしい!
時は2019年5月。アメリカ大陸を渡り歩いた大冒険を終え、ついに3週間ぶりに祖国・日本の土を踏んだ。そして本日で帰国4日目。キューバ滞在に伴って野菜という文明の象徴が圧倒的に不足した結果、筆者の腸はストライキ[…]
おいおいキューバ人頼むぜ~(゜.゜)筆者は2018年と2019年で合わせて17日ほどキューバに滞在し、様々なものを見たり聞いたり多くの人と触れ合う中で「自分の人生観が広がったな」と本当に思いました。そう思わせてくれた[…]
どうも、旅する歴史マニア(見習い)のRYOである。今回の記事では、これからキューバに行こうと目論むそこの君、そう、そこの旅人予備軍のために──いや、正確には未来の自分のために、キューバの歴史をギュギュっとまとめてみた。[…]
2018年4月後半——筆者はついに、あの伝説のカリブ海の浮遊要塞「キューバ」へ、たった1週間という儚くも濃密な旅路に身を投じた。そう、葉巻とクラシックカーとチェ・ゲバラの亡霊が街角で踊るあのキューバである。これはその冒険の全[…]
今回は、キューバの首都ハバナから世界遺産にも登録されている町「ビニャーレス渓谷」への行き方をご紹介する。実はタクシーを使ってもそこまで高くはないのだが、ここではキューバ流、つまりトラック移動に挑戦してみたい。キューバ[…]
皆さんはご存じだろうか?キューバがWi-Fi砂漠であるという事実を…。筆者は現地に降り立って初めて思い知らされた。「フリーWi-Fi? なにそれ美味しいの?」と。そう、キューバには無料Wi-Fiという[…]